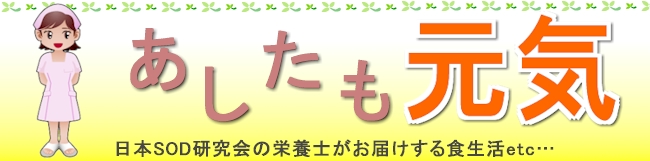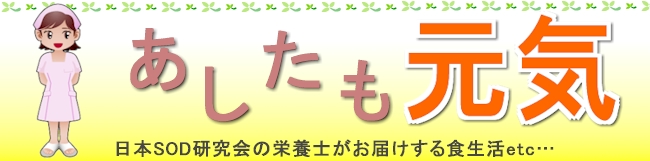|
崪慹闋徢偲偼乧
乽崪慹闋徢乿偙傟偼乽偙偮偦偟傚偆偟傚偆乿偲撉傒傑偡丅
乽慹乿偲偄偆暥帤偼丄傑偽傜偲偄偆堄枴偱乽闋乿偲偄偆暥帤偼丄徏偺梩偑丄僷儔僷儔偲棊偪偰峴偔傛偆側忬懺傪昞偟傑偡丅
偮傑傝丄崪偵乬偡乭偑擖偭偨傛偆偵側偭偨忬懺傪崪慹闋徢偲偄偄傑偡丅
崪慻怐撪晹偵偁傞僗億儞僕忬偺慻怐偺崪検偑尭彮偟丄
崪偑僗僇僗僇偵側傞偨傔崪偼傕傠偔丄崪愜偟傗偡偔側傝傑偡丅偝傜偵愐拰偺曄宍傗崢攚捝偺尨場偲側傝傑偡丅
偱偼丄壗屘崪検偼尭彮偡傞偺偐偲偄偆偲丄
崪傪宍惉偟偰偄傞僇儖僔僂儉晄懌偺怘惗妶傗壛楊偺堊儂儖儌儞偺僶儔儞僗偑曵傟偰偄偔偐傜偱偡丅
崪慹闋徢偼惗妶廗姷昦偺傂偲偮偱丄梊旛孯傕娷傔傞偲慡崙偵栺1000枩恖偄傞偲偄傢傟偰偄傑偡丅
庒偄偆偪偐傜僐僣僐僣偲僇儖僔僂儉傪拁傔丄摨帪偵塣摦偵傛偭偰崪傪抌偊偰偍偗偽杊偖偙偲偑偱偒傞昦婥偱偡丅
傑偨丄偨偲偊50嵨丒60嵨丒70嵨傪寎偊偰傕丄偦偺恖傗偦偺擭楊側傝偺搘椡傪偡傞帠偵傛偭偰丄
偦傟側傝偺岠壥偼摼傜傟傑偡丅
僇儖僔僂儉偲崪
崪偺尨椏偼僇儖僔僂儉偱偡丅僇儖僔僂儉偺99亾偼崪傗帟偵娷傑傟偰偄偰丄
巆傝偼寣塼拞傗嵶朎拞偵娷傑傟偰偄傑偡丅僇儖僔僂儉偺愛庢検偑晄懌偡傞偲寣塼拞偺擹搙傪堦掕偵曐偮偨傔
崪傪梟偐偟偰僇儖僔僂儉傪採嫙偟側偗傟偽側傜偢寢壥丄崪偼梟偗懕偗傕傠偔側傝傑偡丅
崪偼峝偔偰曄壔偟側偄偲巚傢傟偑偪偱偡偑丄
懠偺慻怐偲摨偠傛偆偵屆偄嵶朎偼媧廂偝傟偰怴偟偄崪偑宍惉偝傟偰偄傑偡丅
崪枾搙乮亖僇儖僔僂儉乯偼丄巚弔婜偐傜30乣40嵨戙偵偐偗偰偑僺乕僋偱偡丅
偙偺帪婜偵僇儖僔僂儉傪廫暘偵愛庢偟偰偍偗偽榁壔偵傛傝崪偑懡彮尭彮偟偰傕
崪慹闋徢傪堷偒婲偙偡偙偲偼偁傝傑偣傫丅
仢僇儖僔僂儉傪廫暘偵愛庢偟傛偆両
僇儖僔僂儉偼愊嬌揑偵愛庢偡傞帠偑昁梫偱偡丅
寬峃帪偱偼1擔偵10噐/懱廳噑偑栚埨偲偝傟栺600噐偑惉恖偺強梫検偱偡丅
崪慹闋徢偺恖丄暵宱屻偺彈惈偺応崌偼
800乣1000噐埲忋傪栚埨偵偟傑偡丅
傑偨丄僟僀僄僢僩傪偟偰偄傞恖偼僇儖僔僂儉晄懌偵側傝傗偡偄偺偱婥傪晅偗傑偟傚偆丅
媿擕偼僐僢僾堦攖偱栺
200噐偺僇儖僔僂儉偑愛庢偱偒傑偡丅
懠偺怘昳偐傜傕愛庢偝傟傞帠傪峫偊偰丄1擔2乣3攖堸傓偲傛偄偱偟傚偆丅
媿擕丒擕惢昳偼徚壔媧廂擻椡偺掅壓偟偰偄傞偍擭婑傝偱傕岠棪傛偔愛庢偱偒傑偡丅
媿擕偱壓棢傪偡傞恖偼壏傔偰堸傫偩傝丄備偭偔傝堸傫偩傝椏棟偵巊梡偟偰傝岺晇偟偰傒傞偲傛偄偱偟傚偆丅
傑偨丄壓棢偺尨場偲側傞擕摐傪彍嫀偟偨媿擕傕巗斕偝傟偰偄傑偡丅
| 乻1擔摉偨傝偺僇儖僔僂儉強梫検乼 |
|
擭楊乮嵥乯 |
僇儖僔僂儉乮噐乯 |
| 抝惈 |
彈惈 |
| 0乣6 |
0乣6 |
400 |
| 7乣9 |
7乣8 |
500 |
| 10 |
9 |
600 |
| 11 |
10乣14 |
700 |
| 12 |
亅 |
800 |
| 13乣14 |
亅 |
900 |
| 15乣16 |
亅 |
800 |
| 17乣19 |
亅 |
700 |
| 20乣 |
亅 |
600 |
| 亅 |
擠晈 |
1000 |
| 亅 |
庼擕晈 |
1000 |
|
|
乻僇儖僔僂儉傪懡偔娷傓怘昳乼 |
| 怘昳柤 |
1夞巊梡検 |
僇儖僔僂儉娷桳検 |
| 晛捠媿擕 |
200ml |
200噐 |
| 儓乕僌儖僩 |
100倣倢 |
130噐 |
| 僾儘僙僗僠乕僘 |
20倗 |
126噐 |
| 彫徏嵷 |
80倗 |
232噐 |
| 愗傝姳偟戝崻 |
20倗 |
94噐 |
| 傂偠偒乮姡憞乯 |
10倗 |
140噐 |
| 傢偐傔乮姡憞乯 |
5倗 |
48噐 |
| 偟傜偡姳偟 |
10倗 |
53噐 |
| 幭姳 |
10倗 |
220噐 |
| 傑偄傢偟 |
20倗 |
280噐 |
| 摛晠乮栘柸乯 |
150倗 |
180噐 |
| 惗偁偘 |
50倗 |
120噐 |
| 擺摛 |
50倗 |
45噐 |
|
仢僇儖僔僂儉傪忋庤偵愛庢偡傞偵偼
僞儞僷僋幙丒儕儞丒價僞儈儞D偺僶儔儞僗偑愛傟偰偼偠傔偰寬慡側崪偵側傝傑偡丅
|
佱僞儞僷僋幙佲 |
崪奿偺峔惉惉暘偱偡丅忎晇側崪傪宍惉偟丄僈僢僠儕偲偝偣傑偡丅晄懌偡偮偲僇儖僔僂儉偺媧廂偑埆偔側傝傑偡丅偨偩偟夁忚愛庢偼丄僇儖僔僂儉偺攔煏偑懡偔側傞偺偱揔検傪庣傝傑偟傚偆丅1擔偵擏60乣80倗丒嫑1愗傟丒棏1屄丒摛晠1/2挌埵偑栚埨検偱偡丅 |
|
|
|
|
佱儕儞佲
|
僇儖僔僂儉偲嫤椡偟偰崪傗帟偺峝慻怐傪宍惉偟傑偡丅儕儞丄偼怓乆側怘昳偵娷傑傟偰偄傞偺偱晄懌偡傞偙偲偼傑偢偁傝傑偣傫偑丄夁忚愛庢偺応崌丄偣偭偐偔僇儖僔僂儉傪庢傝崬傫偱傕媧廂偑埆偔側偭偨傝棙梡偝傟偵偔偔側偭偨傝偟傑偡丅
僇儖僔僂儉 丗 儕儞 = 1 丗 1 傕偟偔偼 1 丗 2
偺僶儔儞僗偑岲傑偟偄偲偝傟偰偄傑偡丅壛岺怘昳傗僀儞僗僞儞僩怘昳丄僼傽乕僗僩僼乕僪側偳偼拝怓椏丒擲拝椏丒巁枴側偳偺栚揑偱儕儞巁墫偲偄偆宍偱儕儞偑懡偔娷傑傟偰偄傞偺偱丄婥傪晅偗傑偟傚偆丅
|
|
|
|
|
佱價僞儈儞D佲 |
挵暻偱僇儖僔僂儉偺媧廂傪懀恑偡傞偲摨帪偵崪傊捑拝偝偣傑偡丅價僞儈儞D偑懱撪偱崌惉偝傟傞堊偵偼擔岝偑昁梫偱偡丅晛捠偵惗妶傪偟偰偄傟偽摿偵栤戣偼偁傝傑偣傫丅 |
|
|
|
|
佱偦偺懠佲 |
丒擔崰偐傜堓挵偵晧扴傪偐偗側偄傛偆偵偟傑偟傚偆丅懡検偺堸庰丒媔墝丒僇僼僃僀儞丒墫暘愛庢丅
丒偙傑傔偵懱傪摦偐偟傑偟傚偆丅嶶曕傗懍曕偒側偳壸廳傪偐偗偨壐傗偐側塣摦偑岠壥揑丅 |
|